国産SAFの旗手としてコスモエネルギーHDが挑む
次世代エネルギー戦略
コスモエネルギーホールディングス株式会社
代表取締役社長
山田 茂 氏

廃食用油などを再利用してつくる次世代の航空燃料「SAF」。国内で初めて国産SAFの大規模生産を開始したのが、コスモエネルギーグループだ。石油を「社会に不可欠な基盤」としながらも、未来のエネルギーに向けた挑戦を加速している同社が描く「Vision 2030」とは。次世代エネルギー戦略の全貌に迫る。
コスモエネルギーホールディングス(以下、コスモエネルギーHD)は2025年4月、国内初となる国産SAF(持続可能な航空燃料)の大規模生産を開始した。すでに全日本空輸、日本航空、DHLなどへの供給が始まり、供給先は着実に広がっている。
このSAF事業は、21年にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の公募に他社含む4社で共同提案した「国産廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築」が採択され、コスモエネルギーHDが中心となって推進してきたものだ。構想から4年、代表取締役社長 山田 茂(以下、山田)は「ようやく他社に先駆けて先進的な取り組みができるようになった」と語る。
この言葉の裏には、同社が歩んできた厳しい道のりがある。
11年に発生した東日本大震災では、主力の千葉製油所が大規模火災に見舞われ、操業の停止が長期化。復旧には莫大なコストと時間がかかり、財務基盤は大きな打撃を受けた。さらに17年以降は業界再編が進み、エネオスの再編や出光とシェルの統合によって、石油大手の勢力図が大きく変わった。山田は「業界再編のなかで、自社のポジションには強い危機感を抱いていた」と語る。
コスモエネルギーHDはこの逆境を出発点に、18年以降、財務改善と効率化に徹底して取り組んだ。5年間で体制を立て直し、「財務基盤は他社と遜色ない水準に回復し、効率性については誇れるレベルに達した」と山田は話す。こうして積み重ねた改革は、新たな挑戦への力となった。
「石油を必要とする領域は数多く存在します。だからこそ安定的に供給し続けることが私たちの責務です。その一方で、未来を変える次のエネルギーにも挑戦する。こうした両輪の方針を、18年の第6次連結中期経営計画から現在に至るまで社内外に示しています」
その延長線上にあるのが、既存の精製技術やインフラを活かせるSAFだ。ジェット燃料で培った供給体制を土台に、大阪府堺市にある堺製油所にSAF製造装置を新設し、SAFの大規模生産開始を実現させた。
石油を基盤にグリーン電力と
次世代エネルギーへ
23年、コスモエネルギーHDは「Vision 2030」を掲げ、長期的な方向性を明確にした。中期計画が3年ごとの実行計画を示すのに対し、同ビジョンは10年先を見据えた羅針盤である。石油の安定供給という責務を果たしつつ、グリーン電力や次世代エネルギーといった新たな選択肢を育てる──その姿勢を社会に示した。
「石油は引き続き社会を支える基盤です。しかし将来は電化が進み、自然エネルギーによって発電されたグリーン電力で供給することが求められます。そしてSAFや水素といった次世代エネルギーは、不透明ながらも大きな可能性を秘めている。だからこそ三つの柱を掲げ、現実のニーズに応えつつ、未来を築く道筋としています」
三本柱は互いに補完し合う関係にある。石油事業で培った技術やインフラを次世代エネルギーに応用し、電化が進む社会をグリーン電力で支える。そのなかで最初に具体化したのがSAFだ。
「世界的に旅客数や貨物輸送が増え続けるなか、航空燃料の需要は今後も拡大していきます。その持続可能性を確保する解決策のひとつがSAFです。大規模な生産や供給網の整備を現実的に担えるのは、既存の製油所や輸送インフラを活かせる石油会社ならではの強みです。私たちはインフラ企業としての責務を果たしつつ、既存事業とのシナジーを事業の成長機会へとつなげるために、SAFを次世代エネルギー事業の柱のひとつとしました」
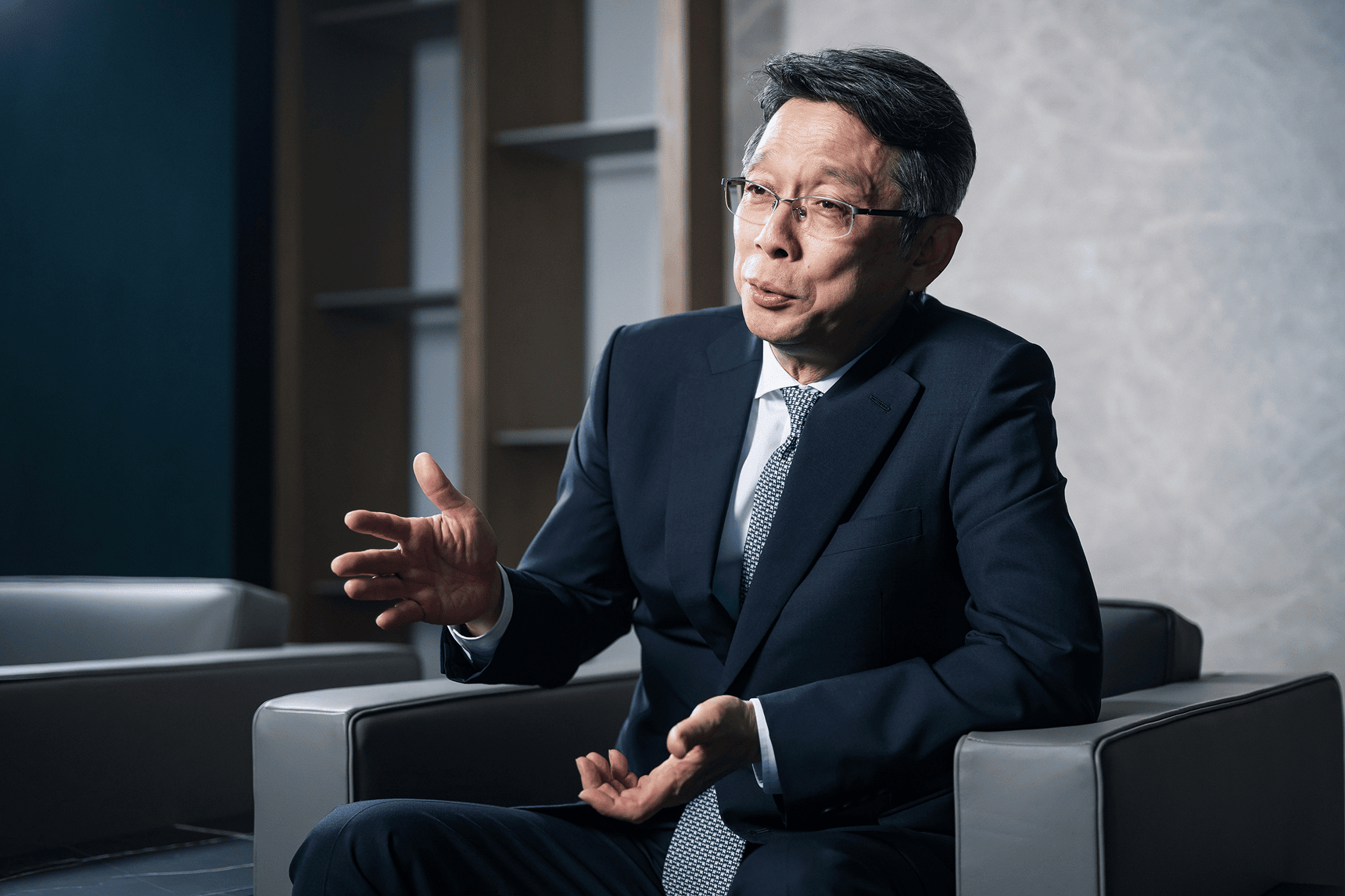
SAFは石油精製のプロセスを活かせる隣接分野であり、同社が長年強みを持つジェット燃料供給の延長線上にある。また、水素についても将来的な成長分野と位置づけており、その取り組みは別途進められている。
こうした挑戦を支えているのは、同社の文化と体制にあるといえるだろう。15年に持株会社体制へ移行し、コスモエネルギーホールディングスとなったが、現在も経営と現場の距離が近く、意思決定の速さは損なわれていない。山田は「私は現場を回って直接社員の声を聞く機会を増やすことを心掛けています。グループ各社も縦割りに陥らず、役割を分担しながらフラットに連携できている」と語る。
その基盤の上で、SAF事業はグループ内外の強みを結集して進められた。22年に日揮ホールディングス、コスモ石油、レボインターナショナルの3社で設立した「SAFFAIRE SKY ENERGY(サファイア・スカイ・エナジー)」を通じて事業を展開。日揮ホールディングスがSAF製造事業に関するサプライチェーンの全体構築を担い、コスモ石油が安定的な製造・供給、コスモ石油マーケティングが航空会社などへの販売を担当する。また、原料となる廃食用油は、長年リサイクル燃料事業を手がけてきたレボインターナショナルが収集・輸送を担う。
コスモエネルギーグループは、グループ各社の結束と外部パートナーの技術と知見を組み合わせることで、原料の調達から製造、供給までを一貫する国産SAFサプライチェーンを築き上げた。
石油事業で磨いた規範を未来へ。
SAFの基盤づくりをリードする
供給にこぎつけたことで、新たな課題も浮かび上がった。政府が掲げる「2030年に国内航空燃料の10%をSAF化」という目標には約170万キロリットルのSAFが必要だ。
しかし日本国内で排出される廃食用油は年間50万トン程度にとどまる。そしてSAFに転換できるのはその何割かにすぎない。廃食用油だけでは到底賄いきれないのが現実だ。山田は、課題解決には国全体での協力が不可欠だと強調する。
「航空分野の脱炭素は、原料の供給を含め、一社や一業界だけでは成し遂げられません。日本全体で廃食用油を効率的に集め、資源を循環させる仕組みをつくることも重要だと考えています」
またSAF以外にも、日本のCO2排出量の約2割を占める運輸部門の削減として、水素ステーションの基盤整備にも踏み出している。大型トラックやバスといった商用輸送分野での実用性を見据え、資本提携を結ぶ岩谷産業と連携しながら、インフラ体制の強化を進めている。
「水素がいつ、大きく普及するかは誰にも断言できません。しかし、だからこそ可能性のある領域に今から取り組んでおくことが重要です。供給基盤を先に整えておけば、需要が立ち上がる局面で必ず強みになります」
このような取り組みを一過性に終わらせないために、同社は6つの価値観を行動規範として社内に浸透させてきた。これからも大切にしたい価値観である「誠実・共生・安全」に加え、これからより重要になる価値観として「挑戦・自発・進化」を新たに掲げ、社員が困難に直面したときの指針としている。
「失敗を恐れず、自ら考え挑戦し、その結果として進化する。従来の価値観を否定するのではなく重ね合わせることで、未来に挑む文化をつくりたい」
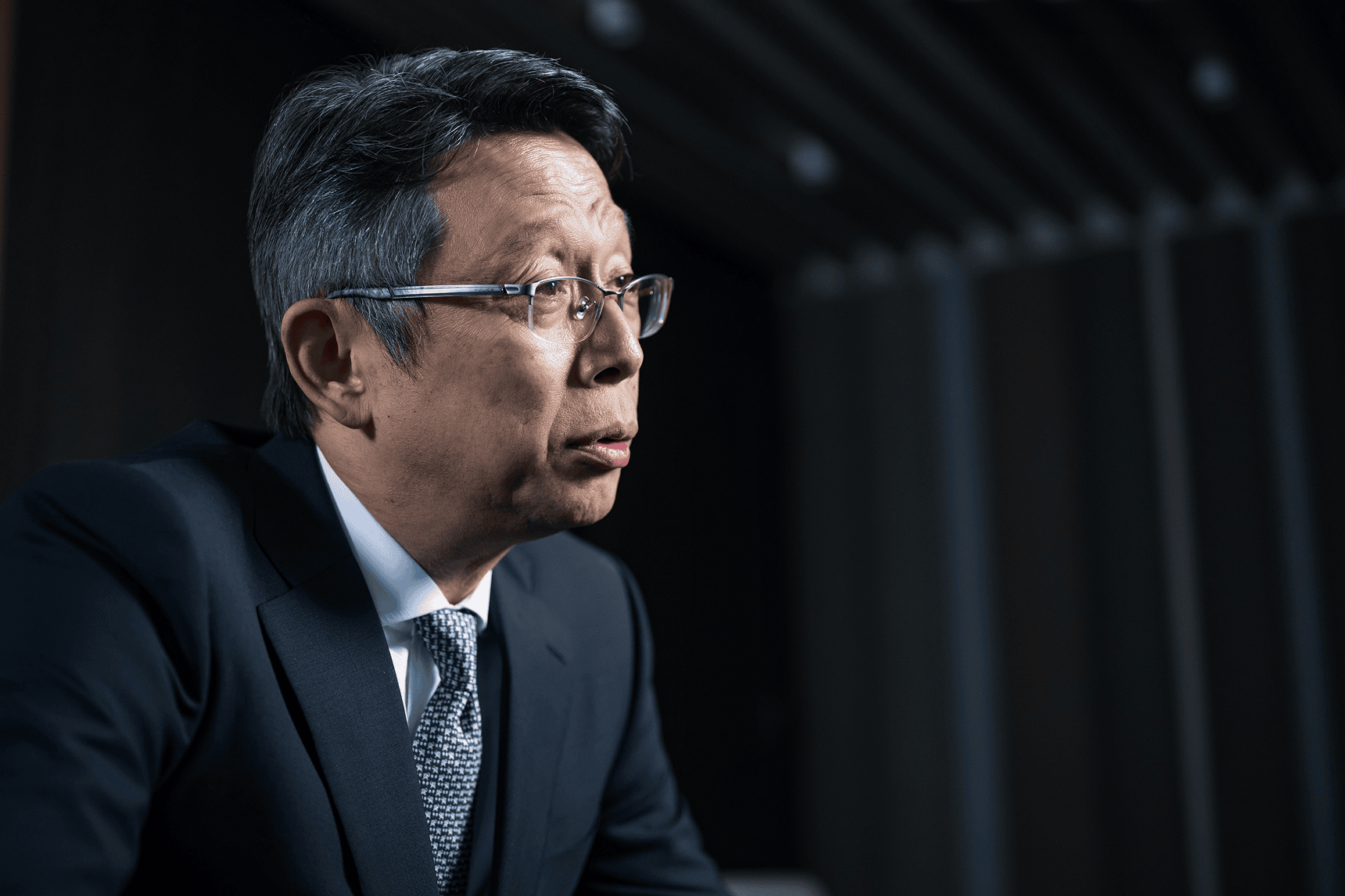
エネルギーは社会の血流であり、途切れさせることは許されない。だからこそコスモエネルギーHDは、石油の安定供給を維持しながらも、SAFや水素、グリーン電力といった次の選択肢を一歩ずつかたちにしている。課題を直視しつつ挑戦を重ねる姿勢こそが、国産SAFの旗手として未来を切り拓く原動力になっている。
「Forbes JAPAN BRANDVOICE」2025年10月17日広告記事より転載(禁無断転載)




